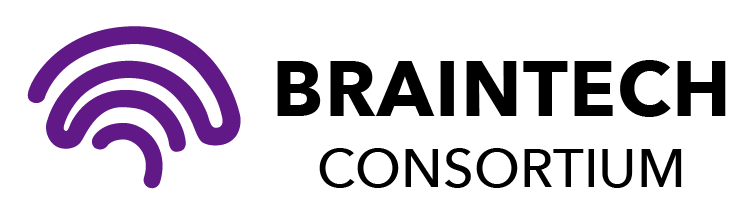BTC – ブレインテック・コンソーシアム › Braintech Crossing › ブレイン・テック ガイドブック ご意見フォーラム › ブレイン・テックの発展に必要な取り組みや制度とは?
- このトピックには5件の返信、2人の参加者があり、最後に
Jakeにより2年、 10ヶ月前に更新されました。
-
投稿者投稿
-
-
2022年10月22日 4:09 PM #7933
 BTC事務局キーマスター
BTC事務局キーマスター消費者目線で考えた場合に、今回の資料はリテラシーを高めるのに非常に役立つと思いつつ、リテラシーがそれほど高くなくとも、適切な製品等を選べるような仕組み(何かしらの基準をクリアしているマークなど?)があると良いかと思いました!
事業者目線で考えた場合には、エビデンスが公開されていない理由として、検証はしていても公開のリスクがあったり、メリットがなかったり という点が公開しない理由なのかと思ったため、消費者目線側でも記載したマーク等の取り組みなどで、公開のメリットを作るなどがあると良いのかと思いました! -
2022年10月23日 11:58 AM #7944
まる
ゲスト技術者目線としてコメントさせて貰います。海外の高性能脳波計は技適認証が取得されていないものも少なくなく、国内での利用難易度の高さを感じることが多いです。工学系でない研究室の学生などだと意外と電波法を知らずに購入・利用している事もあったりするので、「予め知らなくても問題がない」程度にブレインテックのエコシステムを構築する側で一定数、大手海外デバイスの技適取得を行ってくれたらなぁと感じています。メーカー側は日本を市場として見てないことも多く、自主的に取得していないケースも珍しくないのでどこかしら大きい団体がその部分を担ってくれないと「じゃあ海外で同じサービス作る方が楽だわ」ってなってしまう気がしています。
-
2022年10月23日 1:57 PM #7945
Y.K
ゲスト30代男性です。消費者として興味もってます。
脳関連で心配だからリスク関連の事がわかりやすくまとまってるのはありがたいです。認証機関とかで一応大丈夫ですよ認定マークみたいのあると消費者的にはわかりやすいなぁ。信頼できるとこから買いましょうって、色々買いてあるけどやっぱ第三者から意見聞きたいから相談窓口ほしいな~。違法の通報窓口とかよりよっぽどその情報がほしいw
あと口コミとかも読みたいです、窓口とかで情報管理されすぎちゃうとそれはそれで不安
わがまま言ってすいません! -
2022年10月24日 9:47 AM #7948
西下 慧
ゲストデバイスの進化が必要かと思います。
スマートウォッチのように人々が日常生活で装着できるレベルのものが出てくると、脳活動を日常的に取得でき、消費者にとっても便利なサービスが出てくるかと思いました。
これはかなり先の話かもしれませんが、デバイスを装着するのではなく、非接触で脳活動を取れるようになるとブレイクスルーが起こるような気がしています。例えば、店舗に来店したお客さんの脳活動からおすすめの商品を提示したりすることもしやすくなるかと思いました。脳活動の取得については当然、個人の同意は必要ですが、顧客に脳デバイスをつけてくださいというのは現状、かなりハードルがあるように感じます。 -
2023年3月21日 6:19 PM #8111
Jake
ゲストHey!
-
-
投稿者投稿
- フォーラム「ブレイン・テック ガイドブック ご意見フォーラム」には新規投稿および返信を追加できません。